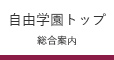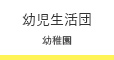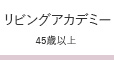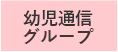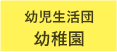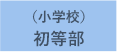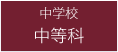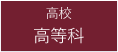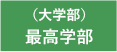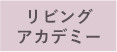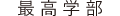6月10日(月)
アウシュヴィッツ博物館の訪問は、今回の研修旅行のプログラムの中でも重要なものの一つでした。
今回、日本人正規職員の中谷剛さんにガイドしていただき、他の日本人見学者も合わせて20人ほどで、約4時間かけて第一・第二収容所跡を廻りました。
学生たちは、今回の訪問を前に『夜と霧』(ヴィクトール・E・フランクル)を読むことを必須としました。また、先月日本公開が始まった映画「関心領域」も旅行直前に鑑賞した学生もいました。
学生の日報から
過ちを繰り返さないために、過去を知ることの意味がようやくわかった気がする。
私は歴史の授業が苦手だ。過去の出来事を時系列に沿って覚える作業だと思っているからだ。
時には、こういう要因があってこんな結果になりました、という話を授業でされることもあるが、だからと言って、それが現代に通ずるような話ではないと思っていたからだ。
今回、中谷さんの案内のもと、アウシュビッツを見て回って、彼が時々問いかけてくることが印象的だった。
民主主義とは何か。ヒトラーを選んだのは誰なのか。
博物館では民主主義が崩壊する過程をよく表している。
ただ残忍な行為が行われていただけではなくて、どのようにして、どんな残忍なことがあったのかを知ること、人間が人間を選別すること、争いによって命の重さが変わってしまうこと。今、パレスチナやウクライナが大変な時に、ここに来られたことの意味を問えること。
過去を見た自分が、問いを持って今を見ることができ、かつこれからをつくる立場であることを実感を持って再認識する機会となった。
しかし、正直に言えば、アウシュビッツの見学はあと2、3回ほどしなければ消化しきれないと感じている。
それだけ過去は重く、複雑で、考えなければならないことがたくさんあるのだ。
今後も、私たちの生活は続く。
どこかで戦争が起こっていても、離れていればそれを忘れてしまうし、かわいそうとは思っても、自分たちの知らない感覚には、同じように共感することができるわけでもない。
ならば、それを知らない人たちには何ができるのだろう。
人と人が対等であるには、1人の痛みに皆が寄り添うためには、どうしたらよいのか。
言葉ひとつ取っても、受け取り方が変わる。疑い、問いかけ続けることが、今できる最大限のことなのだろうか。







中谷さんから次々に発せられる問いの数々に、学生たちはこの悲劇が過去のものではなく、ポーランドの隣国ウクライナや世界で日々繰り返されていること、日本の戦争体験、政治との向き合い方、多くのことを考えながら過ごしました。
展示、風景、それら全てが悲惨な歴史を物語っており、特に第二収容所(ビルケナウ)見学中には風雨が強くなり一層壮絶な雰囲気を感じられました。
文・写真:咲花昭嗣(最高学部教員)、恵木美折(最高学部2年)